
こんにちは。やもともりです。
小学5年生の娘は、幼稚園年長のときから先取り学習を続けています。
進研ゼミ小学講座を【1つ上の学年】で登録し、一年分を先に学習する形です。

娘
現在は小5で、「小6のチャレンジタッチ」に取り組んでいます。

やもともり
チャレンジタッチのタブレットも、だいぶ年期が入ってきました。
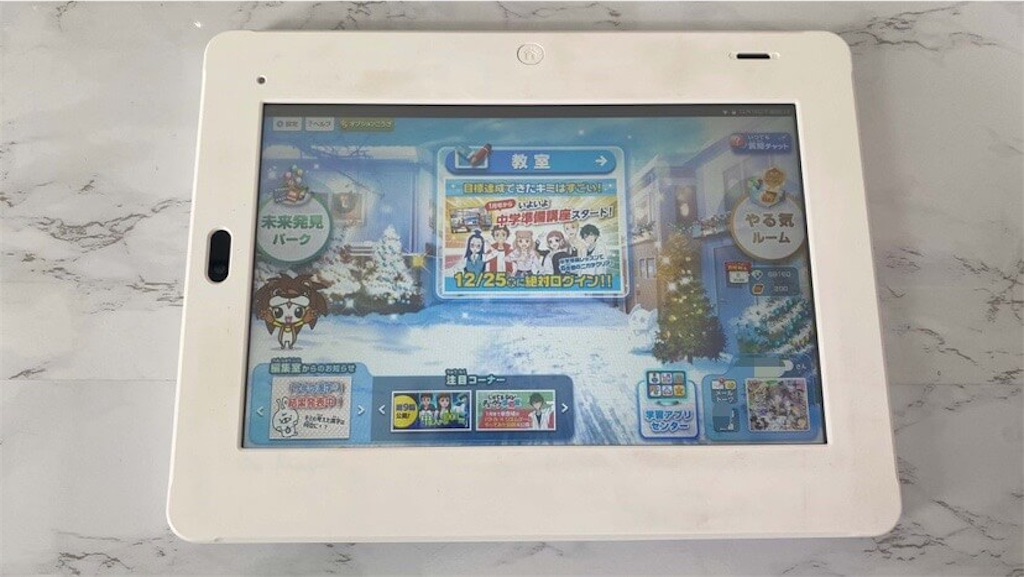
娘は自ら進んで勉強するような、勉強大好きな子ではありません。それでも毎日よく頑張っており、成績は今のところ良好。中学受験の予定はなく、学びと遊びのバランスが取れています。
そのため私は、今後もチャレンジタッチで先取り学習を続けていけば安心だと思っていました。
そんな私が娘の今後の学習方法について考え始めたのは、進研ゼミから中学講座の案内が届いたからです。
中学の学習内容では覚える量が増え、難易度もぐっと上がります。一年分の先取り学習を続けることは、娘の負担が大きくなるかもしれません。
このまま進研ゼミの中学講座を申し込んでいいのか迷うなぁ。
そこで、娘の今後の学習方法について、家族で話し合うことにしました。
スポンサーリンク
先取り学習のメリットを感じているか確認

まずは「先取り学習のメリットを感じているか」について確認することにしました。
先取り学習の主なメリット
- 教育熱心なご家庭を見ても焦らなくなる
- 余裕を持って勉強できる
- 「勉強が得意」という自信がつく
1つ目のメリット「教育熱心なご家庭を見ても焦らなくなる」については、親の都合です。
残りの2つのメリットについて娘に確認したところ、学校の授業は理解しやすく、余裕を持って受けることができているそうです。勉強が得意かどうかは、「少しそう思う」という回答でした。
次に、先取り学習のデメリットについて。
先取り学習の主なデメリット
- 授業がつまらなくなる可能性がある
- 難しすぎると自信を失う
- 予習時期が早すぎて内容を忘れる
娘に確認したところ、やる前から結果を知っている理科の実験はつまらない時があるそうです。難し過ぎて自信を失うことはない、とのこと。予習が早すぎて内容を忘れるかどうかは、「大体覚えているけど細かいところは忘れてしまっている」と言っていました。
以上の結果、娘にとって先取り学習のメリットは有効であり、デメリットは想定の範囲内だと感じました。
そのため、少なくともあと一年間は先取り学習を続けることにしました。

やもともり
小学6年生の忙しさは、きっと今と同じくらい。中学1年生の学習内容に取り組む時間はありそうです。
どの方法で先取り学習を続けるか

小学生のうちは、先取り学習を続けることになりました。娘が小学6年生になったら、中学1年生の学習内容を予習し始めます。
そこで、次に家族で話し合ったのは「どの方法で先取り学習を続けるか」についてです。
話し合いの中では以下の学習方法を候補に挙げて、娘の意見を聞きました。
- 通信タブレット学習(進研ゼミなど)
- オンライン動画で学習(スタディサプリなど)
- 問題集や参考書の活用
- 予習型の塾に通う
- 家庭教師を頼む
①通信タブレット学習(進研ゼミなど)
通信教育で専用のタブレット端末を使って学習する方法。進研ゼミ、スマイルゼミ、Z会など。
メリット
- 好きな時間に自分のペースで学習を進められる
- 専用のタブレット端末を使って学習でき、学習進捗の管理や自己採点の機能も充実している
- 塾や家庭教師と比べると費用が抑えられる
デメリット
- 自主性がないと継続が難しい
- 直接指導がないと疑問点の解消に時間がかかる

娘
タブレット学習は慣れているから続けやすそう。
②オンライン動画で学習(スタディサプリなど)
オンラインの授業動画を観て学習する方法。「スタディサプリ」や「東進オンライン学校」など。
メリット
- 好きな時間に自分のペースで学習を進められる
- 一流講師の授業動画が豊富
- 塾や家庭教師と比べると費用が抑えられる
デメリット
- 自主性がないと継続が難しい
- 直接指導がないコースだと、疑問点の解消に時間がかかる
- 専用の端末がなく自宅の端末(スマホなど)を使うので、つい別のアプリも開きたくなる

娘
短めの動画だったら集中して観られそう。
③問題集や参考書の活用
紙の問題集や参考書を使って学習する方法。
メリット
- 好きな時間に自分のペースで学習を進められる
- 塾や家庭教師と比べると費用が抑えられる
- 自分のレベルや好みに合った本で学習できる
デメリット
- 自主性がないと継続が難しい
- 直接指導がないと疑問点の解消に時間がかかる
- 進捗状況の管理が難しい
- 自分のレベルや好みに合った本を探すことに手間と時間がかかる

娘
私は音や映像がある教材の方がいいなぁ。
④予習型の塾に通う
予習型の学習塾に通うという方法。個別指導と集団指導がある。
メリット
- 友達と一緒に学ぶことでモチベーションが上がる
- 適度な緊張感があり、集中できる環境が整っている
- 時間が決まっているので強制力が働く
- 疑問点を質問しやすい
デメリット
- 通塾のための時間と労力がかかり、時間に縛られる
- 自分のペースで学習を進められない
- 教師との相性や教師の力量で学習効果が左右される
- 受講する教科が多いと費用が高くなる

娘
夜に通うのは大変そう。
⑤家庭教師を頼む
家庭教師に個別指導をしてもらう方法。対面型だけではなくオンライン型もある。
メリット
- 個別指導のため、子どもの学力やペースに合った指導が受けられる
- 疑問点をその場ですぐに質問できる
- 苦手分野に特化した学習も可能
デメリット
- 指導者との相性や指導者の力量が学習成果に影響する
- 時間に縛られる
- 費用が高い

娘
一対一の指導は、今は必要ないと思う。
以上5つの学習方法の中から娘が選んだのは、タブレット学習でした。これからも進研ゼミのタブレットで自分の好きな時間に学習したいそうです。
夫と私も、娘の意見に賛成。来年の4月から「中学1年生の内容」を予習できるように、進研ゼミ中学講座を申し込みました。

やもともり
家庭教師を希望されたら家計が厳しくなるので、内心ひやひやでした。
娘の負担が増え過ぎないように、学習の休息日を提案

娘が小学6年生になったら、中学1年生の内容を学び始めます。再来年、中学1年生になったら、部活動も始まりさらに忙しくなります。
難しさや忙しさが増すばかりでは息が詰まりますよね。そこで、学習の休息日を作ることを提案しました。

やもともり
進研ゼミの内容が難しくて負担が増えてきたら、週に1回は学習をお休みしよっか。

娘
えっ、毎日じゃなくていいの?やったー!
娘の理解度や興味に合わせて、先取り学習の内容やペースを調整する必要も出てくるでしょう。
休息日に気持ちをリフレッシュしながら、無理なく先取り学習を続けてもらえたらと思っています。
おわりに

進研ゼミ中学講座の案内が届いたことをきっかけに、娘の今後の学習方法について改めて考えることができました。
結果的に、小学生のうちは今まで通り「進研ゼミのタブレット」で先取り学習を続けることに決まりましたが、他の学習方法を視野に入れる良い機会となりました。
娘は4月からは小学6年生、そして再来年度には中学生になります。これからも学習内容や生活リズムの変化に柔軟に対応できるよう、親としてサポートしていきたいです。

















