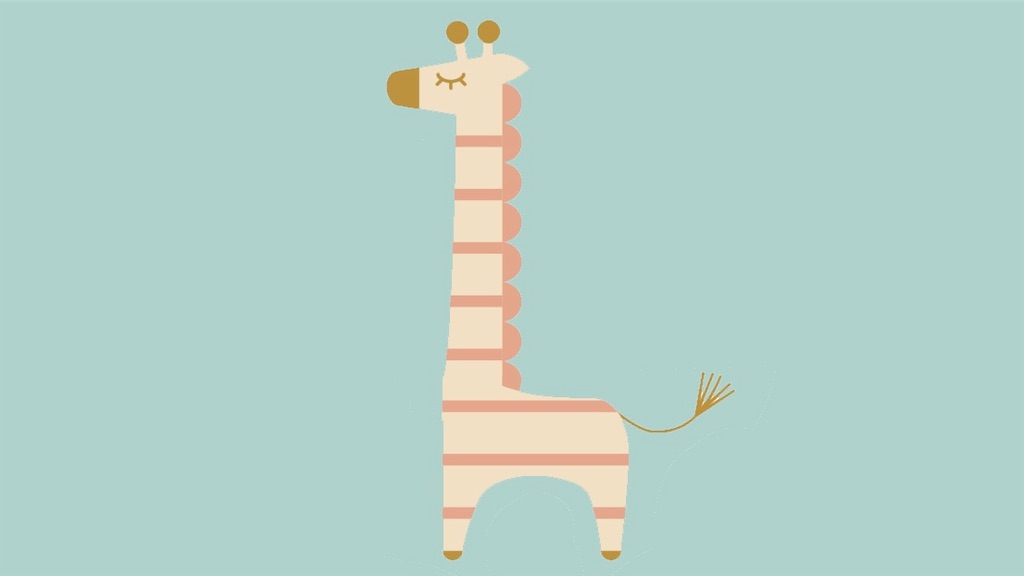
こんにちは。やもともりです。

やもともり
今回の記事では、少子化について思っていることを書きます。
スポンサーリンク
- 理性は「子孫を残すという本能」にブレーキをかけることがある
- 先進国で少子化が進む主な理由
- 心配性の私も、「子どもが欲しい」とは思っていなかった
- 欲しいと思っていなかったものが、急に欲しくなるときもある
- 子育て支援の限界と、少子化でも成り立つ社会作りへのシフト
- 実際のところ、私にできる少子化対策は?
- 子育て中の不安をやわらげる言葉
- 欲張らず、少子化の中で生きていく
理性は「子孫を残すという本能」にブレーキをかけることがある
キリンの首が長くなったのは、「高いところの葉っぱを食べたかったから」と思われがちですが、それは正確ではありません。実際には、「突然変異でたまたま首の長いキリンが生まれ、その特徴が生存に有利で子孫を残しやすくなった」と考えられています。運よくそのときの環境に適応できた個体が生き残る。進化とは、そういうものです。
しかし、人間は少し違います。他の動物とは異なり、人間は「考える生き物」。理性で現状を冷静に把握し、将来を想像します。人間の理性は、繁殖という本能的欲求にブレーキをかけることがあります。そのため、必ずしも「生存に有利な人が子孫をたくさん残す」とは限らないのです。
先進国で少子化が進む主な理由
実際、日本のような先進国では、以下のような理由から「子どもを作らない」という選択をする人が増えています。
- 子育てには手間もお金もかかり責任も発生し、自分のために使う時間やお金が減る
- 自分一人が生きていくのにも精一杯
- 特別な支援が必要な子が生まれた場合、育てられるか不安
- 環境問題、大地震などの天災、財政破綻など、心配ごとの多い世の中に生まれる子どもは気の毒
- 自分の人生が楽しくなかったため、子どもに同じ思いをさせたくない
- 自分のことが好きではないから、自分の遺伝子を残したくない
- 一人でも楽しく生きられる社会では、結婚や子どもは必要ない・女性の社会進出が進み、「結婚や出産が当たり前」と言う風潮が薄れてきた
- そもそも子どもが欲しいと思わないから、子育て支援が手厚くなっても気持ちは変わらない(納豆が苦手な人は納豆を値下げされても買わないし、みんなが食べていても納豆の栄養を説明されても食べないのと同じ。)
心配性の私も、「子どもが欲しい」とは思っていなかった
私自身も、以前は「子どもを作らない」という選択をしていた一人でした。特に「心配ごとの多い世の中に子どもを残すのは気の毒だ」と強く感じていました。それに、そもそも「子どもが欲しい」と思っていなかったのです。
欲しいと思っていなかったものが、急に欲しくなるときもある
それなのに私は、8年前に娘を出産しました。「子どもを欲しい」と思うようになったのは、世間体や親の期待を気にした訳ではなく、時間的・金銭的な余裕ができて気持ちが変わった訳でもありません。
理性に変化はありませんでした。本能が、大きく働いたのです。
親友が赤ちゃんを産み、抱っこしている姿を見たときに、なぜだか急に子どもが欲しくなりました。それまでも他の友達の赤ちゃんを見て可愛いと感じることがありましたが、「私も欲しい」と思ったのは初めてでした。
嫉妬や憧れもあったかもしれませんが、それよりももっと心の奥底の、本能が目覚めたかのようでした。「自分の中のもう一人の自分」が子どもを欲しがっているように感じました。
心配性で深く考える癖がある私にしては珍しく、将来を不安に思う「理性」よりも、子どもが欲しいという「欲望」の方がずっと大きくなったのです。結婚前には「子どもはいなくてもいい」と話していた私が「子どもが欲しい」と突然言い出したので、夫はとても驚いていました。
人間には理性があります。そして感情も本能も備わっています。そのため、とても不安定な生き物です。欲しくても理性で諦めるときがありますし、欲しいと思っていなかったものが急に欲しくなるときだってあります。
今の若い世代の人たちは結婚や出産に消極的な傾向があると言われていますよね。さまざまな考えの人がいて、それぞれが色々な事情を抱えているため、私は無責任に結婚や出産をオススメする気は全くありません。でも、「年を重ねて気持ちが変わる場合もある」ということは伝えておきたいです。
子育て支援の限界と、少子化でも成り立つ社会作りへのシフト
子どもを欲しいと思った人が、安心して子どもを産める社会。政府は日本がそういう社会になるように、子育て支援を頑張ってくれています。
ただ、私は子育て支援をこれ以上拡大しても、少子化に歯止めをかけることは難しいと感じています。
いくら金銭面で支援の強化があっても、「金銭以外の面で大きな不安を抱えている人」には響きませんよね。
望んでいても結婚や妊娠がかなわない人もいますし、結婚や子育てどころではないほど苦しい環境で生きている人もたくさんいます。それに、「そもそも子どもが欲しいと思わない」という人の気持ちを変えることは、とても難しいです。
子育て支援は大切ですが、「子ども欲しがる人を増やす効果」については限定的です。
だからこそ、少子化対策は、「少子化に歯止めをかけること」よりも、「少子化でも成り立つ社会作り」を考えて進めていく方が現実的だと思います。【人口が減り経済成長が縮小しても、成り立つ社会】を作ることに注力するのです。
日本の国土や資源を考えると、必ずしも今の人口規模を維持する必要はないのかもしれません。無理に子どもを産ませて人口を維持しようとせず、そういう時期だと受け入れる。欲しいと思う人だけが、育てられる人数だけ産めばいいのです。
労働人口の不足については、AIやロボットでカバーしていく時代です。熟練者が減少するこれからの社会では、AIが技術と知識を次世代に橋渡しする役割を担います。
もちろん、少子高齢化では国民年金などの面で苦しい世代が発生しますが、長い歴史を見ればそういう時期は何度もありました。少なくとも20年以上は苦しい時期が続くと予想されますが、苦しい世代の生活を国債の発行などで支援しながら、人口構造の偏りが徐々に改善されるのを見守っていきます。
高齢者が多い社会では医療費をいかに抑えていくかについても大きな課題です。私は「延命医療」の内容について見直しが必要だと考えています。たとえば、回復の見込みが低い高齢者に対する高額かつ長期の延命措置(人工呼吸、胃ろうによる人工栄養、人工透析など)については、原則として控える方針への転換を検討すべきではないでしょうか。延命措置を医療保険の対象外とし、本人や家族が強く希望する場合に限り私費で行う仕組みも、一つの選択肢として議論されるべきです。不自然な延命が減ることで、結果として国民医療費の抑制につながる可能性があります。
人口が減少することでたくさんの問題は生まれますが、最新技術の活用や、従来の制度の見直しなどによって一つずつ解決していけたらいいなと思います。それに、人口が減少することで、「他の社会問題」が自然と解決に向かう可能性があることも覚えておきたいところです。(例えば、スペースや資源の分配に余裕が生まれるなど。)
実際のところ、私にできる少子化対策は?
ここまで色々な可能性を述べてきましたが、国の制度が変わることや理想論を抱くだけでは何も変えられません。
政治家でも権力者でもない私に何ができるのか。実際にできることを考えてみました。今のところ2つあります。
一つ目は、【欲張らず、8割でよしとすること】です。
「仕事のキャリアは捨てたくない。子どもは欲しい。自分の時間も欲しい。」などと全てを同時に叶えることは難しいです。体力も時間もお金も有限なのだから、何かを取るなら何かを妥協する必要があります。
欲張る気持ちを減らす人が一人でも増えれば、足りていない人を助けることに繋がります。もちろん、人間の欲がきっかけでたくさんの技術が生まれてきましたが、足りていない人の存在を置いてけぼりにしてはいけません。
つい、「もっと欲しい、もっとこうしたい」と欲張ってしまうときには、過去を振り返ると落ち着きます。江戸時代や戦時中の人々の生活を想像すると、現代の日本は私にとって十分幸せな場所だと気づくことができます。
二つ目は、【余裕があるときは誰かを手伝うこと】です。
余裕があるときは、余裕が無い人や困っている人を助けること。家族を助けることはもちろん、「家族以外の人」のためにも自分の時間と労力を分けられたら素敵だなと思っています。
本当に、ちょっとしたことでいいのです。例えば、前から来る人に道を譲ったり、困っている人に声を掛けたり。SNSのコメントに親身になって返信したり。
このブログでも、効率化や節約や子育てに関する工夫についての記事をあげています。読んでくれた人のお金や時間に少しでも余裕が生まれ、悩みを軽くできたら嬉しいと思いながら書き続けています。
子育て中の不安をやわらげる言葉
誰に頼まれたわけでもなく、私は自分のエゴで、覚悟を持って娘を産みました。産んで後悔したことは一度もなく、愛おしい存在を授かったことに感謝しています。大変なことも妥協することもありますが、これまで感じたことがなかった種類の幸せを日々味わえています。もともとたくさん子どもが欲しいとは思っていなかったので、もし子育て支援がより手厚くなっても二人目が欲しいとは思わないでしょう。
日本や地球の将来に対する不安は、子どもを産む前と後とで変わっていません。暗いニュースを目にすると、娘に対して「こんな世の中に産んでごめんね」と思いそうになります。
しかしそんなときは、すぐに前向きな言葉に言い換えます。「どんな世の中でもしなやかに生きられる力をつけられるよう、サポートするね。」
褒め方や叱り方の工夫をして、子どもの自己肯定感や自己効力感を育てていきます。挑戦や試行錯誤を温かく見守りながら応援。楽しく効率的に学べる環境を整え、これからの社会に必要な力を身につけるサポートをします。特に、論理的に考える力や、英語力、AI関連の知識については、将来欠かせないものです。
娘の生きる未来は必ずしも明るいものではないかもしれません。だからこそ、今のうちからたくさんの幸せを感じてもらえるよう、娘のやりたいことをできるだけ叶えて、毎日を笑顔で過ごしたいです。
欲張らず、少子化の中で生きていく

キリンの首が長くなったのは、たまたま首の長いキリンが生まれ、その特徴が生存に有利で子孫を残しやすくなったと言われています。もし、高いところにある葉っぱを欲張って独り占めせず、家族や仲間にも分けていたら、もっと多種多様なキリンが存在していたかもしれません。
キリンなど他の動物とは異なり、人間は「考える生き物」。
人間は、葉っぱを食べられない仲間の気持ちを考えられる生き物です。多様性を大切にしようという意識を持ち、その考えを大勢と共有できる生き物です。
欲張る気持ちを少し減らし、奪い合わず手を取り合えば、少子化を受け入れて暮らしていける。私はそう信じています。
ロザンさんのYouTube動画(【オススメ本】『生物はなぜ死ぬのか』)
首が長いキリンが生存に適していた理由としては、「高いところの葉っぱを食べられる」ことのほかに、「遠くの敵を見つけやすい」、「配偶者を巡る争いで優位に立てる」などの説もあります。
















